先日レビューを書いた映画『幕が上がる』の原作小説を読み終え、すがすがしい余韻に浸っているところです。たしかにこれを読めば登場人物たちをももクロに当てはめた本広克行監督の“発見”もごくごく自然なことだったと分かります。当て書きなんじゃないの?って思う。思うよこれは監督。
当たり前っちゃあ当たり前ですが、原作では、演劇部を急激にレベルアップしてくれた元学生演劇の女王・吉岡先生に対する主人公・さおりの気持ちが映画以上に克明に描かれていて、さおりが何を考え、行動したかがより分かりやすくなっています。
映画は2時間という制約があるので、どうしても心理描写を端折ったり濃縮したりしなきゃいけない。それを思うと、原作の持ち味を損なうことなく2時間の物語に収めた喜安さんの脚本に感服。
小説は、さおりの細やかな視点を百田夏菜子さんで脳内再生するのが楽しくて楽しくて、そうとうに贅沢なディレクターズ・カット版を観たような満足感がありました。
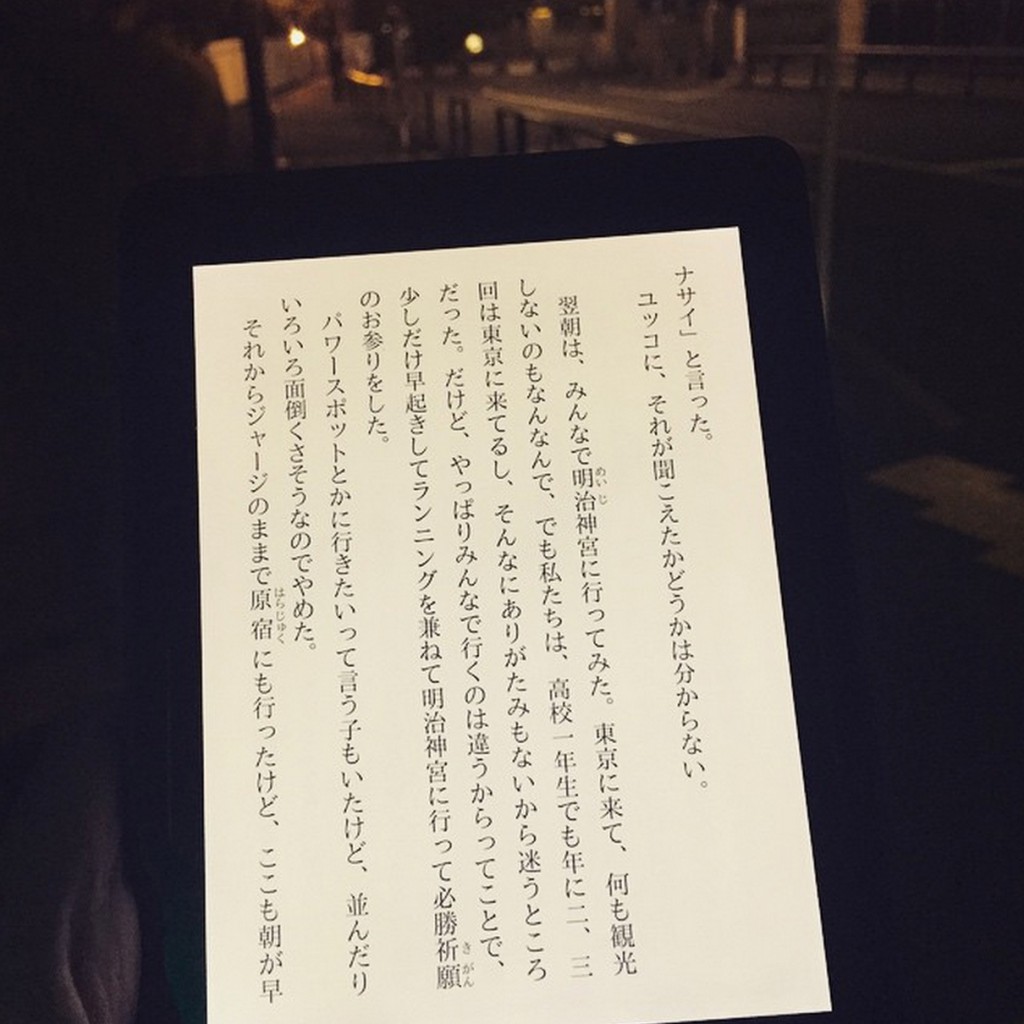
中学時代ほど自由闊達に夢を追い続けにくくなってくる高校生という季節。部活に情熱を注ぎながらも進路を考えなければいけない3年生のふつうの女の子が、それでも部活の先に見た夢に向かって駆け抜ける。原作者が劇作家の平田オリザさんだからこそ、平田さんの人間観察と演技指導の流儀が作品から見えてきて、キャラクターの魅力が増幅されてゆく。スーパーポジティブでもスーパーネガティブでもない“平熱”からすこしずつ上昇する物語は、平田さんの提唱される「現代口語演劇」そのもの。
いま売られている雑誌『FLIX』の中で、平田オリザさんはこう語っています。
「小説を出したとき、登場人物が良い子ばかりだという指摘もあったけれど、僕は主人公のトラウマ設定とかが好きじゃないんです。今の物語ってそんなのばっかりじゃないですか。どうもお手軽に思えて、この小説はそういう設定や展開は一切なしで書いてみようと決めた。実際に、演劇をやっている子たちを指導しても、本当にみんな良い子たちで、そりゃ悩みも抱えているけれど、それを虐待とかいじめの社会問題につなげたくはない。そのこだわりは映画にも活かしてもらえましたね」
(別冊FLIX 3月号より)
トラウマを描かずにドラマをつくるって、いちばん難しいことなんじゃないか。
映画の公開は今月末からですが、先に原作を読んでみてもいいかもしれません。平田さんはご自身のBlogか何かでその順をオススメされていました。平田オリザさん、信じられる。
昨年観たのは三谷幸喜さんの『紫式部ダイアリー』1本と、しばらく足が遠のいていた演劇に再び興味が沸いてきたので、平田さん主宰の青年団若手公演『南へ』のチケットを買ってみました。楽しみ。